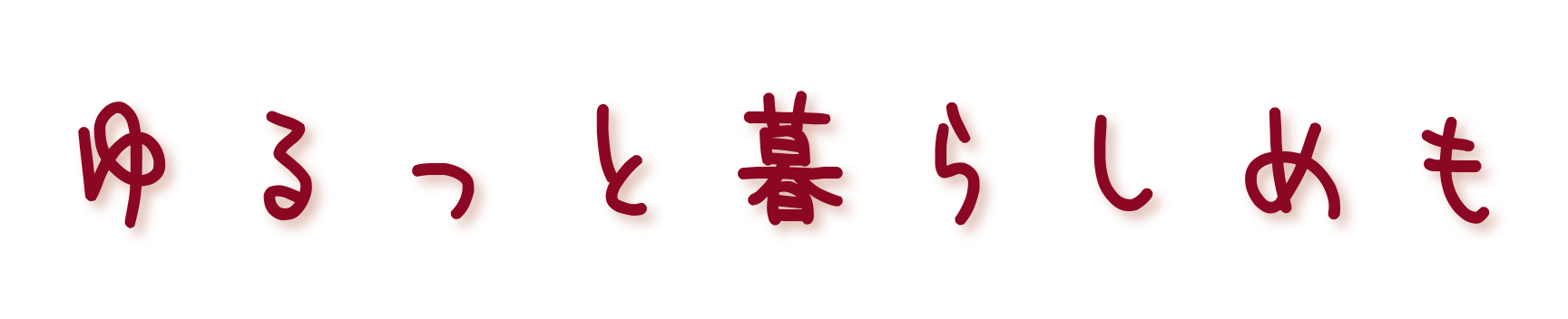初詣でお参りをしたあと、絵馬に願い事を書く人も多いのではないでしょうか。
小さな木の板に書かれた一文字一文字には、「今年こそ叶えたい想い」が込められています。
けれども、「正しい書き方がわからない」「何を書けば願いが届くの?」と迷うこともありますよね。
絵馬は、神様や仏様へ願い事を“見える形”で伝えるための大切な道具。
書き方や奉納のマナーを知ることで、気持ちをより深く込めることができます。
この記事では、絵馬の意味や由来、正しい書き方と奉納マナー、願いが叶いやすくなるコツを紹介します。
新しい年の願いを、心を込めて届けましょう。
目次
絵馬とは?その意味と由来
初詣で多くの人が願いを込めて書く絵馬。
あの小さな木の板には、実は長い歴史と深い意味が込められています。
現代では「願い事を書くもの」というイメージが強いですが、もともとは神様や仏様への感謝や祈りを表す“供え物”の一つでした。
絵馬の歴史と成り立ち
絵馬の起源は、古代の日本にまでさかのぼります。
昔は、神様に「願いが叶いますように」と本物の馬を奉納する風習がありました。
しかし、すべての人が馬を奉納できるわけではなかったため、次第に木や紙に馬の絵を描いて奉納するようになったのが「絵馬」の始まりです。
平安時代には貴族の間で広まり、江戸時代には庶民も手軽に奉納できるようになりました。
やがて馬の絵だけでなく、健康・学問・縁結びなど、願い事の内容に合わせたさまざまな絵柄が描かれるようになります。
神社とお寺での絵馬の違い
神社では、神様に願いを「届ける」ために奉納します。
一方、お寺では仏様に「祈りを捧げる」意味合いが強く、絵柄も穏やかなものが多いのが特徴です。
どちらも共通しているのは、「言葉にすることで願いを明確にし、自分の気持ちを整理する」ということ。
絵馬は単なる風習ではなく、“祈りの形”として現代まで受け継がれています。
絵馬の書き方の基本
絵馬は、願い事を「文字にして神仏へ伝える」ための神聖なもの。
だからこそ、書き方にも心を込めたいものです。
難しい決まりはありませんが、昔から大切にされてきた基本のマナーや書き方を知っておくと、より丁寧に祈りを届けることができます。
願い事の書き方
まず、絵馬の裏面に願い事・名前・日付を書くのが一般的です。
願い事は「○○できますように」よりも「○○になります」と断定的・前向きな言葉で書くのがポイント。
神仏にお願いするというより、自分の誓いを形にするイメージで書くと、より強い気持ちを込められます。
名前や日付を書くのは、“誰の願いか”を神仏に明確に伝えるためです。
文字の向きやペンの種類
文字の向きは、絵馬の絵柄がある面を上にして、裏面の木目に沿って横書きにするのが一般的です。
筆ペンやマジックなど、消えにくいペンを使うのがおすすめ。
鉛筆やボールペンは、雨や風で薄くなることがあるため避けましょう。
また、丁寧に清書する気持ちを大切にすることで、心も自然と落ち着きます。
避けたほうがいい書き方
「誰かが不幸になりますように」など、他人を不幸にするような内容は避けましょう。
また、複数の願いを詰め込みすぎると、気持ちが散漫になりがちです。
願いは一つに絞り、具体的で前向きな言葉を選ぶことで、誠実な祈りとして神仏に届きやすくなります。
願いが叶いやすくなるコツ
絵馬に願い事を書くとき、ただ「○○したい」と書くだけではなく、気持ちの込め方や言葉の選び方にも少し意識を向けると、より思いが届きやすくなるといわれています。
ここでは、絵馬を通して願いを実現へと近づけるためのちょっとしたコツを紹介します。
願いを「一つ」に絞る
人は複数の願いを持ちたくなるものですが、絵馬には“ひとつの想い”を込めるのが基本です。
願いを一つに絞ることで、心が迷わず、神仏に届く力も強まるといわれています。
どうしても複数の願いがある場合は、それぞれ別の絵馬に書くのがおすすめです。
一枚一枚に集中して書くことが、祈りを深める秘訣です。
言葉をポジティブに書く
願い事は、「〜できますように」よりも「〜になります」「〜を達成します」と、前向きで具体的な言葉で書くと良いとされます。
これは、神仏へのお願いというより、“自分自身の誓い”に近い考え方。
ポジティブな言葉を使うことで、自分の意識も自然と前向きになり、行動にも良い影響を与えてくれます。
感謝の言葉を添える
絵馬には、願いと一緒に「いつも見守ってくださりありがとうございます」などの感謝の言葉を添えるのもおすすめです。
感謝の気持ちは、神仏との信頼を深め、運を引き寄せるといわれています。
「ありがとう」という言葉を添えるだけで、文字に込めるエネルギーがぐっと優しく、温かいものに変わります。
絵馬を奉納する手順とマナー
絵馬を書いたあとは、神様や仏様に気持ちを届けるために奉納します。
どこに、どんな順番で掛ければいいのか迷う人も多いですが、基本の流れとマナーを知っておけば大丈夫。
ここでは、初詣のときに役立つ奉納の手順と注意点を紹介します。
奉納のタイミング
絵馬は、参拝を済ませてから奉納するのが一般的です。
まずは神様や仏様に新年のあいさつをして感謝の気持ちを伝え、そのあとで絵馬を書き、奉納します。
先に絵馬を書いてしまうと、願い事だけを先に伝える形になるため、順番には少し気を配りましょう。
絵馬掛け所での正しい掛け方
絵馬は、神社やお寺の境内にある「絵馬掛け所(絵馬掛)」に奉納します。
掛ける位置に決まりはありませんが、無理に上の方を狙う必要はありません。
空いている場所に、静かに・丁寧に掛ければ十分です。
掛ける際は、心の中で改めて願いを唱えると、より祈りが深まります。
他人の絵馬を見るのはOK?
多くの人が奉納している絵馬には、それぞれの真剣な想いが込められています。
興味本位で内容を覗き込むのは避けましょう。
ただし、テレビや観光ガイドなどで紹介されている「有名人の絵馬」などは、公開を前提に掛けられている場合もあります。
基本的には、“見るより、自分の願いに集中する”ことが大切です。
書いた絵馬はどうなるの?
心を込めて書いた絵馬。
奉納したあと、それがどうなるのか気になったことはありませんか?
実は絵馬は、一定期間神社やお寺に掛けられたあと、きちんとお焚き上げ(おたきあげ)という儀式で祈願が届けられます。
ここでは、奉納後の絵馬がたどる流れを紹介します。
奉納後の扱いとお焚き上げ
奉納された絵馬は、一定期間境内に掛けられたあと、神職や僧侶によってお焚き上げの儀式が行われます。
お焚き上げとは、火の神の力で祈願を天へと届ける行為。燃やすことで、願いを清めながら神仏に感謝を伝える意味があります。
年末年始や節分などの節目に行われることが多いです。
願いが叶った後の絵馬の返納
願いが叶ったときは、感謝の気持ちを込めて改めて絵馬を奉納するのがおすすめです。
新しい絵馬に「願いが叶いました。ありがとうございました」と書いて納める人もいます。
感謝の心を形にして返すことで、さらに良いご縁が続くといわれています。
持ち帰った絵馬はどうすればいい?
一部の神社では、記念として絵馬を持ち帰ることもできます。
持ち帰った場合は、家の神棚や玄関など、明るくて清潔な場所に飾っておきましょう。
飾ることで、願いを忘れずに努力を続ける“お守り”のような存在になります。
願いが叶ったら感謝を込めてお焚き上げに出すのが理想です。
さいごに
絵馬に願い事を書くことは、神様や仏様に祈りを届けるだけでなく、自分自身の目標や気持ちを“言葉にする”という意味もあります。
文字にして書き出すことで、心が整理され、やるべきことが少しずつ見えてくるものです。
願いを絵馬に込める瞬間は、未来への小さな約束のような時間。
神仏に任せるだけでなく、「自分も努力して叶えよう」という気持ちを持つことが、願いを実現へと導く第一歩です。
そして、願いを書いたことを忘れずに、日常の中で感謝の気持ちを持ち続けましょう。
毎日を大切に過ごすことが、絵馬に込めた願いを現実へと近づける何よりの力になります。