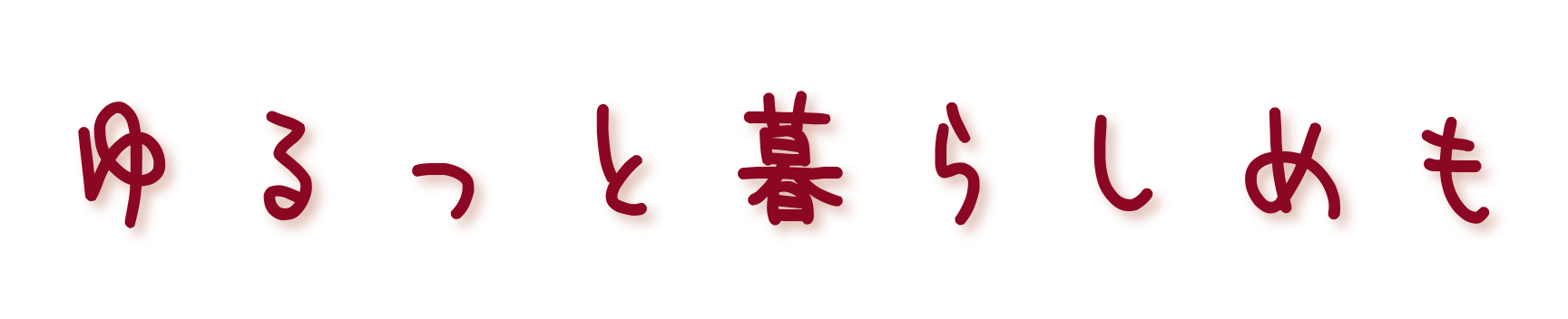近年は年賀状よりもLINEやSNSで新年の挨拶を交わす人が増えています。
しかし身近な人が亡くなり喪中のとき、「LINEで新年の挨拶をしていいの?」「グループでのやりとりにはどう反応すればいいの?」と迷う場面も少なくありません。
喪中はがきの代わりにLINEで伝えるケースもある一方で、マナーを誤ると相手に不快な思いを与えてしまう可能性もあります。
本記事では、喪中のときにLINEで新年の挨拶をどうするべきか、個人宛・グループ宛・返信やスタンプの使い方まで具体的に解説します。
これを読めば、年始のやりとりを安心して乗り切れるはずです。
目次
喪中のときにLINEで新年の挨拶はしていいの?
喪中のとき、新年の挨拶をLINEで送るべきかどうかは迷いやすいポイントです。
基本的には年賀状と同じ考え方で「新年を祝う言葉は控える」のがマナーとされています。
ただし、相手との関係性ややりとりの流れによって柔軟に対応することも可能です。
基本は年賀状と同じで控えるのがマナー
喪中の際は「あけましておめでとう」という言葉を避けるのが基本です。
LINEも同じで、年始のメッセージを積極的に送るのは控えた方が無難です。
どうしても伝えたい場合は「本年もよろしくお願いいたします」など、お祝いのニュアンスを含まない表現を使うのが安心です。
H3:相手から挨拶が来たときの返信方法
相手が喪中を知らずに「あけましておめでとう」と送ってきた場合は、無視する必要はありません。
返信するときは「お心遣いありがとうございます。本年もよろしくお願いいたします」といった形で、祝い言葉を避けつつ感謝を伝えるのがよいでしょう。
相手に気まずさを与えない自然な対応を心がけることが大切です。
H3:親しい友人・同世代へのカジュアルな対応
親しい友人や同世代の相手なら、LINEで「今年もよろしくね!」などと軽く返すのも許容されます。
あえて堅苦しい表現を避けることで、距離感を崩さずに済むケースもあります。
大切なのは相手との関係性に合わせて、形式にとらわれすぎず柔軟に言葉を選ぶことです。
喪中のときのグループLINEでの対応
友人や職場のグループLINEでは、年明けに「明けましておめでとう!」という一斉の挨拶が飛び交うことがよくあります。
喪中のときはどう反応すべきか迷いやすい場面ですが、無理に合わせる必要はなく、控えめな対応で問題ありません。
一斉の「あけましておめでとう」にどう反応するか
グループ全体に対しては、必ずしも挨拶を返す必要はありません。
喪中であることを詳しく説明するのは場の空気にそぐわないため、かえって気を遣わせてしまうこともあります。
スタンプや短いコメントで軽く反応する程度にとどめると、自然で違和感のない振る舞いになります。
コメントせずに既読で済ませてもいい?
大人数のグループLINEでは、既読だけで流してもマナー違反にはなりません。
全員が一斉にやりとりする場なので、個々の事情まで説明しなくても理解されやすいです。
どうしても気になる場合は、特に親しい人にだけ後から個別で一言添えておけば安心です。
控えめな返信の仕方
喪中でありながらも何か返したいときは、「本年もよろしくお願いします」「今年も仲良くしてください」などシンプルな表現が適しています。
お祝いの言葉を避けながらも、前向きなニュアンスを残せるのがポイントです。
過度に暗くならず、自然に関係性を保てる一言を選ぶとよいでしょう。
喪中の人にLINEを送るときのマナー
相手が喪中の場合、新年の挨拶をどう送るかは悩むところです。
LINEは気軽に使えるツールだからこそ、言葉選びやタイミングに注意しないと失礼に感じられることもあります。
ここでは喪中の相手にLINEを送るときのマナーを整理してみましょう。
「おめでとう」は避けて無難な挨拶を
喪中の相手に「あけましておめでとうございます」と送るのは不適切です。
代わりに「今年もよろしくお願いします」「寒い日が続きますがお元気ですか」など、お祝いを含まない表現にしましょう。
短い一文でも、相手を気遣う気持ちが伝われば十分です。
「寒中見舞い」に切り替えたメッセージも使える
年明けから1月7日(松の内)を過ぎたら、「寒中見舞い」としてのメッセージを送る方法もあります。
LINEでも「寒中お見舞い申し上げます」と始めれば、喪中相手にふさわしい挨拶になります。
文章の最後に「健康にお気をつけてお過ごしください」と添えると、形式に沿いつつ温かみのあるメッセージになります。
短くても気遣いが伝わる一文の工夫
LINEは手軽さが特徴なので、長文でなくても問題ありません。
「昨年はお世話になりました」「本年も変わらずよろしくお願いします」といった一文だけでも十分気持ちは伝わります。
大切なのは形式よりも「気遣う心」であり、余計な言葉を避けつつシンプルにまとめるのがポイントです
喪中のときに使えるLINEの文例集
具体的な文例を知っておくと、いざメッセージを送るときに迷わず安心です。
ここでは喪中の場面で使える、個人宛・グループ宛・返信などの文例を紹介します。
スタンプや絵文字の選び方もあわせて押さえておきましょう。
個人宛に送るときの文例
- 「昨年は大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。」
- 「寒さ厳しい折ですが、お体に気をつけてお過ごしください。」
シンプルで丁寧な言葉を選べば、祝いを避けながらも誠実さを伝えられます。
グループ宛で使える短い挨拶例
- 「本年もよろしくお願いします!」
- 「今年も仲良くしてくださいね。」
カジュアルなグループなら短い一言で十分です。
余計な説明をせずに自然なやりとりに合わせましょう。
相手から届いたメッセージへの返信文例
- 「ご丁寧にありがとうございます。本年もよろしくお願いいたします。」
- 「お気遣いいただきありがとうございます。どうぞお体にお気をつけてお過ごしください。」
祝いの言葉を避けながらも、感謝を伝えることで好印象になります。
まとめ|LINEでも相手に配慮した挨拶を心がけよう
喪中のときは、LINEでも基本的に「新年を祝う言葉」を控えるのがマナーです。
とはいえ、完全に沈黙するのではなく、「本年もよろしくお願いします」など控えめな表現でつながりを保つことはできます。
グループや個人宛て、返信の仕方など状況に応じた対応を心がければ、相手にも気を遣わせずに済むでしょう。
スタンプや絵文字も落ち着いたものを選べば、気持ちを添えることができます。
形式にとらわれすぎず、相手への思いやりを第一に考えることが、喪中の挨拶で最も大切なポイントです。