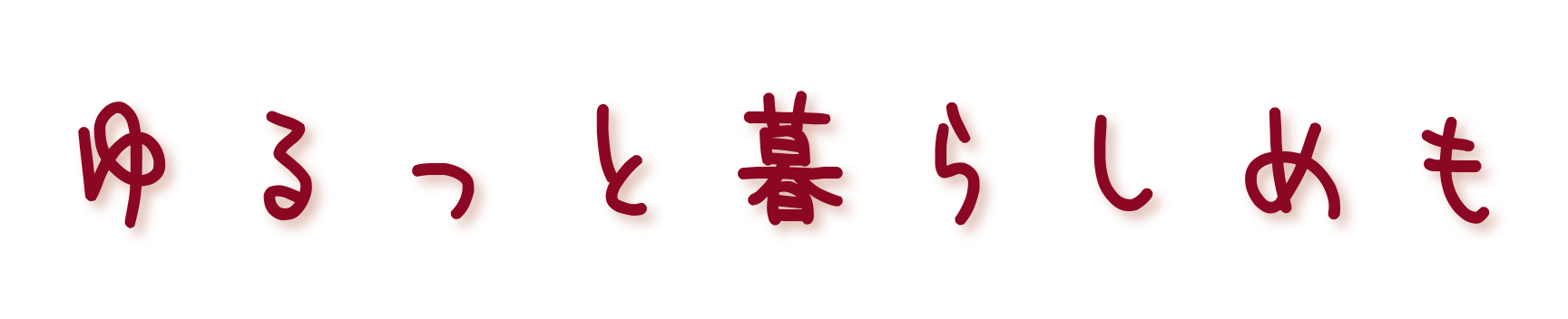身近な人が亡くなった際、翌年の新年の挨拶を控えることを伝えるのが「喪中はがき」です。
普段はあまり馴染みがないため、いざ自分が出す立場になると「いつ出すのが正しいの?」「誰に送ればいいの?」と迷う人も多いでしょう。
喪中はがきは年賀状のやりとりを控えるだけでなく、故人を偲びながら相手に配慮を示す大切な挨拶状です。
本記事では、喪中はがきの基本的な役割や意味から、出す時期、送る相手、文面の構成まで、初めての人でも分かりやすいようにまとめました。
これを読めば安心して準備を進められるはずです。
目次
喪中はがきとは?基本の役割と意味
喪中はがきは、年賀状の代わりに出す挨拶状です。
身内の不幸があったことを知らせるとともに、新年の祝賀を控える気持ちを伝える役割を持っています。
普段のはがきや手紙と違い、形式的なものではありますが、相手への思いやりを込めて出すことが大切です。
年賀状を控えるための挨拶状
喪中はがきは、翌年の年賀状を送らないことを知らせる目的で出されます。
相手が年賀状を準備する前に伝えることで、相手にも無駄な手間をかけずに済むという配慮につながります。
結果的に、自分自身の喪に服す気持ちと、相手への思いやりを両立する挨拶状といえるでしょう。
故人を偲びつつ新年の挨拶を遠慮する意味
喪中はがきには、故人の死を悼む気持ちとともに「新年の祝いを控える」という意味があります。
単に「年賀状を出さない」と伝えるだけでなく、悲しみの中で迎える新年には祝い事を避けたいという心情を表しています。
送る側の気持ちをさりげなく伝える手段でもあるのです。
一般的な送付の流れ
喪中はがきは通常、11月から12月初旬にかけて投函されます。
相手が年賀状の準備を始める前に届くようにするのが基本です。
はがき自体は郵便局や印刷サービスで手軽に用意できますが、文面には故人との関係や逝去日を簡潔に記載し、必要以上に詳細を書かないのがマナーです
喪中はがきを出す時期とタイミング
喪中はがきは、相手が年賀状を準備する前に届くことが大切です。
時期を誤ると相手に迷惑をかけてしまう場合もあるため、目安となるタイミングを知っておく必要があります。
ここでは一般的な出す時期や、遅れてしまった場合の対応について解説します。
11月〜12月初旬が目安
喪中はがきは11月から12月初旬にかけて出すのが一般的です。
相手が年賀状を書き始める前に届くようにするのが理想で、特に12月上旬までに相手に届けば失礼にあたりません。
早めに準備しておけば、落ち着いて対応できるでしょう。
遅れてしまった場合の対応
12月中旬以降に喪中はがきを出すと、すでに相手が年賀状を投函している可能性があります。
その場合は、届いた年賀状に返礼をしないのではなく、年明けに「寒中見舞い」で挨拶を返すのがマナーです。
喪中を伝えるのが遅れてしまったとしても、きちんと気遣いを示せば相手に失礼にはなりません。
地域や習慣による違い
喪中はがきを出す時期には地域差もあり、早めに出す習慣のあるところや、12月中旬でも問題ないとされるケースもあります。
大切なのは「相手に迷惑をかけないこと」なので、迷ったときは早めに出すのが安心です。
印刷サービスや郵便局でも、11月頃から注文や販売が始まるため、その時期を目安にするとよいでしょう。
喪中はがきを送る相手と送らなくてもよい相手
喪中はがきはすべての人に出す必要はなく、送るべき相手とそうでない相手があります。
誰に出すかを見極めることで、無駄を省きつつ、相手への配慮を適切に示すことができます。
ここでは送る相手と不要な場合について整理します。
年賀状をやりとりしている人には必ず出す
普段から年賀状を交換している相手には、喪中はがきを必ず出しましょう。
特にビジネス関係や親しい友人には、年末までに届くように準備することが大切です。
相手に「年賀状を出してもいいのか」と迷わせないためにも、早めの連絡が望ましいです。
喪中を知らない相手には早めに知らせる
相手が喪中を知らない場合、普通に年賀状を準備してしまうことがあります。
そのため、特に遠方の知人や疎遠になっている親戚などには、喪中はがきを出して知らせるのがマナーです。
突然の訃報を兼ねて伝える場合もありますが、簡潔で落ち着いた文面にすることが求められます。
家族や近しい人には不要な場合も
家族や日常的に交流がある人には、喪中はがきを改めて出す必要はありません。
すでに事情を理解しているため、年賀状のやりとりを控えることも自然に伝わっています。
ただし親族でも遠方に住んでいる場合や、普段あまり顔を合わせない場合は出した方が丁寧です。
喪中はがきの文面の基本構成
喪中はがきの文面はシンプルで構いませんが、伝えるべき内容をきちんと押さえておくことが大切です。
冗長にならず、必要なことだけを簡潔にまとめるのが基本の形です。
ここでは喪中はがきに入れるべき要素を整理します。
冒頭の挨拶文(年賀欠礼の表明)
まずは「喪中につき年始のご挨拶をご遠慮申し上げます」といった年賀欠礼の表明から始めます。
堅苦しく感じる場合は「本年中のご厚情に感謝申し上げます」と感謝の言葉を添えることもあります。
最初に「年賀状は控えます」という趣旨を明確にすることで、相手に誤解を与えません。
故人との関係や逝去日を簡潔に記載
次に、故人が誰であるか、送る側との関係を簡潔に書き添えます。
例えば「○月に父 ○○が永眠いたしました」といった形で、詳細を長々と書く必要はありません。
相手が故人を知らない場合もあるので、必要最小限の情報にとどめるのがマナーです。
結びの言葉と相手への感謝
最後に「皆様には良い年をお迎えくださいますようお祈り申し上げます」といった結びの挨拶で締めます。
新年の祝いを避けながらも、相手の健康や幸せを祈る一文を添えることで、冷たい印象にならず思いやりが伝わります。
短い言葉の中に感謝と配慮を込めることが大切です
まとめ|喪中はがきは相手への思いやりを伝える大切な習慣
喪中はがきは、単に「年賀状を出しません」と知らせるだけでなく、故人を偲びながら新年の祝いを控える気持ちを伝える大切な挨拶状です。
時期や送る相手、文面のマナーを守れば、相手に不快な思いをさせずに気持ちを届けられます。
形式的に見えても、そこには送る側の心遣いが表れています。
喪中はがきを正しく準備することで、相手との関係を大切にしつつ、新しい年を静かに迎えることができるでしょう。