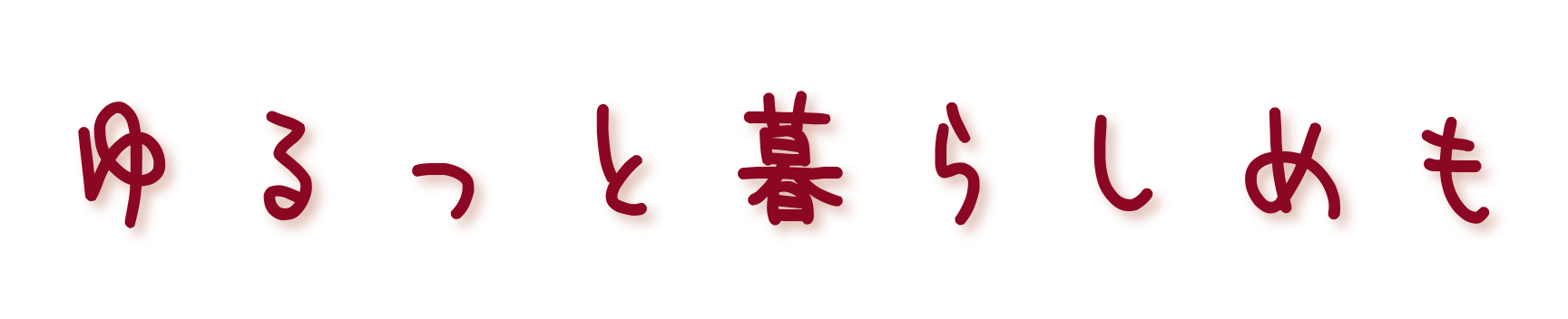新しい一年を迎える初詣のときに、多くの人が「厄祓い」を受けようと神社を訪れます。
厄祓いとは、その年に降りかかるかもしれない災いや不運を祓い清め、健やかで平穏な一年を過ごせるように祈る神事のことです。
特に「厄年」と呼ばれる節目の年齢には災厄が起こりやすいとされ、古くから多くの人が神社で祈祷を受けてきました。
とはいえ、厄祓いの方法や手順をよく知らないまま参拝する人も少なくありません。
受付や初穂料の納め方、祈祷の流れは神社によって違うこともあり、初めてだと不安になることもあるでしょう。
この記事では、初詣に合わせて行う厄祓いの基本や方法、男女別の2025年厄年早見表までをわかりやすく解説します。
厄祓いの意味や参拝の流れを知っておけば、安心して祈祷を受けられ、心新たに一年をスタートできるはずです。
目次
厄祓いとは?
「厄祓い」とは、人生の節目にあたる年齢で起こりやすい災厄を避けるために、神社で祈祷を受ける儀式のことです。
古くから日本では「厄年」と呼ばれる年に注意が必要とされており、特に大厄の年齢は病気や事故など不幸が重なりやすいと信じられてきました。
厄祓いを受けることで、災いを祓い清め、心身を整えて一年を穏やかに過ごすことを願います。
厄祓いは初詣のタイミングで受ける人が多いですが、実際には一年を通じていつでも受けられるものであり、地域や家庭の習慣によっても受け方はさまざまです。
ここではまず、厄祓いの基本を整理してみましょう。
厄年の考え方と「大厄」
厄年とは、人生の中で特に災厄が起こりやすいとされる年齢のことです。
一般的に男性は25歳・42歳・61歳、女性は19歳・33歳・37歳が「本厄」とされ、その前後1年を「前厄」「後厄」と呼びます。
中でも男性の42歳と女性の33歳は「大厄」とされ、特に注意が必要だと伝えられてきました。
もちろん科学的根拠はありませんが、心身や生活の変化が起こりやすい年代であることから、昔から節目の年として受け止められています。
数え年と満年齢の違い
厄年を数える際には「数え年」を用いるのが一般的です。
数え年とは、生まれた年を1歳とし、新しい年を迎えるごとに1歳加算する数え方です。
つまり、誕生日に関わらず、元日を迎えた時点で全員が年を取ることになります。
このため、同じ学年であれば一斉に同じ厄年を迎えることになります。
普段の生活では満年齢に慣れている人が多いため、厄年の判定を誤解しやすい点に注意が必要です。
厄祓いと厄除けの違い
「厄祓い」という言葉は主に神社で使われます。
神職によるご祈祷を通じて、身に降りかかる災いを祓い清めるのが目的です。
一方で「厄除け」は主にお寺で行われる行事で、災厄を寄せ付けないように祈るものです。
お寺では「星祭(ほしまつり)」と呼ばれる行事の一環で厄除け祈願を行うところもあります。
意味合いに大きな違いはありませんが、参拝先によって呼び方が変わると理解しておくと混乱しにくいでしょう。
初詣当日の流れと所要時間の目安
初めて厄祓いを受けるときに気になるのは、「当日はどんな流れで進むのか」「どれくらい時間がかかるのか」という点でしょう。
神社ごとに細かな違いはありますが、基本的な流れは全国ほぼ共通しています。
一般的には、社務所での受付から祈祷の終了までで30分〜1時間程度が目安です。
ただし、正月三が日や大安の日には参拝客が集中し、待ち時間が大幅に伸びることもあります。
家族全員で受ける人や、七五三や安産祈願など他の祈祷と同時に行う人も多いため、思った以上に時間を要するケースも珍しくありません。
ここでは、初詣に合わせて厄祓いを受ける際の標準的な流れを順を追って確認しておきましょう。
受付から申込までの流れ
神社に着いたら、まずは社務所や祈祷受付所へ向かいます。
受付では申込用紙に氏名・住所・生年月日・厄年の区分などを記入し、初穂料を納めます。
のし袋を準備する場合は表書きに「初穂料」または「玉串料」と書くのが一般的で、封筒は白無地か紅白の水引が入ったものを使うと丁寧です。
神社によっては事前に公式サイトから申込書をダウンロードできるところもあるので、混雑を避けたい人は事前準備がおすすめです。
受付が済むと、番号札や整理券を受け取り、待合所で順番が呼ばれるまで静かに待ちます。
ご祈祷から授与品までの一連の流れ
順番が来ると本殿または祈祷殿へ案内されます。
神職が太鼓を打ち鳴らして祈祷が始まり、祝詞で参列者の名前や願意が読み上げられます。
場合によっては玉串奉奠を行い、参拝者が玉串を神前に捧げて一礼することもあります。
祈祷が終わると、お札やお守り、お神酒などの授与品をいただきます。
これらは一年間、自宅の神棚や清浄な場所に祀り、翌年の初詣で古札納所に返納するのが習わしです。
中には「厄割玉」や「身代わり人形」など、独自の授与品を授ける神社もあり、地域の伝統や特色が感じられるのも厄祓いの魅力といえます。
所要時間と混雑の目安
厄祓い全体の所要時間は30分〜60分程度が一般的ですが、時期や神社の規模によって差があります。
たとえば有名な大社や都市部の神社では、正月三が日には数時間待ちになることもあります。
一方で地域の氏神様のような中小規模の神社では、比較的スムーズに受けられることも多いです。
どうしても混雑を避けたい場合は、松の内(1月7日)を過ぎたころや平日の午前中がおすすめです。
また、祈祷は必ずしも初詣の日に限らず、一年を通じて受けられるので、家族の予定や体調を考えて柔軟に調整しても問題ありません。
厄祓いの時期とベストタイミング
厄祓いは「初詣のときに受けるもの」というイメージを持つ人が多いですが、実際には一年を通していつでも受けることができます。
ただし、昔から「年の初めに厄を祓って心新たに過ごす」という考え方が広まっており、年明けから節分(立春前)までの時期に行うのが一般的です。
また、地域によっては特定の祭事や行事に合わせて厄祓いを行う習慣もあります。
ここでは、厄祓いのタイミングについて押さえておきましょう。
初詣から節分までが一般的
もっとも多いのは、正月三が日や松の内(1月7日頃まで)、そして節分までの期間に厄祓いを受けるパターンです。
新年の節目に合わせて心身を清め、安心して一年を過ごしたいという気持ちから、多くの人が初詣と同時に厄祓いを行います。
特に大厄を迎える年は、できるだけ早い時期に祈祷を受けて気持ちを整える人が多い傾向にあります。
年間を通じて受けても問題なし
実は、厄祓いは正月や節分に限らず、年間を通じていつでも受けることができます。
体調が整ったときや家族と予定が合うときなど、自分にとって区切りのよいタイミングで祈祷を受けても問題ありません。
特に仕事や学業の節目、引っ越しや結婚などライフイベントの前に受ける人もいます。
厄祓いは「受けなければいけない日が決まっている」ものではないため、無理に混雑する時期に行かず、落ち着いて参拝できる日を選ぶのも良い方法です。
地域ごとの習慣や神社の行事に合わせる
一部の地域や神社では、節分や立春に合わせた「星祭」や「節分祭」といった行事の中で厄祓いを行う習慣があります。
また、旧暦の正月や地域の祭礼の時期に合わせて祈祷を受けるケースもあります。
その土地の伝統や家族の習慣に従って時期を決めるのも、信仰に即した自然な形といえるでしょう。
事前に公式サイトや社務所に確認して、自分が参拝する神社の慣習を知っておくと安心です。
【保存版】2026年(令和8年)の厄年早見表
2026年(令和8年)の厄年を、男女別・前厄/本厄/後厄に分けて一覧にしました。
数え年の考え方はすでにご紹介した通り、生まれ年を基準に確認できます。
自分や家族が対象かどうか、以下の表でチェックしてみましょう。
男性の厄年早見表(2026年)
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 24歳 2003年 (平成15年) | 25歳 2002年 (平成14年) | 26歳 2001年 (平成13年) |
| 41歳 1986年 (昭和61年) | 42歳 1985年 (昭和60年) | 43歳 1984年 (昭和59年) |
| 60歳 1967年 (昭和42年) | 61歳 1966年 (昭和41年) | 62歳 1965年 (昭和40年) |
女性の厄年早見表(2026年)
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 18歳 2009年 (平成21年) | 19歳 2008年 (平成20年) | 20歳 2007年 (平成19年) |
| 32歳 1995年 (平成7年) | 33歳 1994年 (平成6年) | 34歳 1993年 (平成5年) |
| 36歳 1991年 (平成21年) | 37歳 1990年 (平成2年) | 38歳 1989年 (昭和64年/平成元年) |
| 60歳 1967年 (昭和42年) | 61歳 1966年 (昭和41年) | 62歳 1965年 (昭和40年) |
さいごに
厄祓いは、ただ不安を取り除くための儀式ではなく、心を新たに一年を迎えるための大切な節目でもあります。
厄年は人生の転換点にあたり、体調や生活環境の変化が起こりやすい年代と重なることも少なくありません。
だからこそ、厄祓いを受けることで「気持ちを整える」「前向きに進む」きっかけになるのです。
初詣に合わせて厄祓いを受ける人もいれば、節分や人生の節目に合わせて行う人もいます。
大切なのは「決まりだから」ではなく、「自分や家族の安心のために」祈る気持ちです。
正しい方法や準備を知っておけば、厄祓いは難しいものではありません。
今年が厄年にあたる人も、そうでない人も、神社に参拝して心を整えることは新しい年を気持ちよく始めるための大切な習慣です。
ぜひ厄祓いを通して、清らかな気持ちで新年の一歩を踏み出してください。