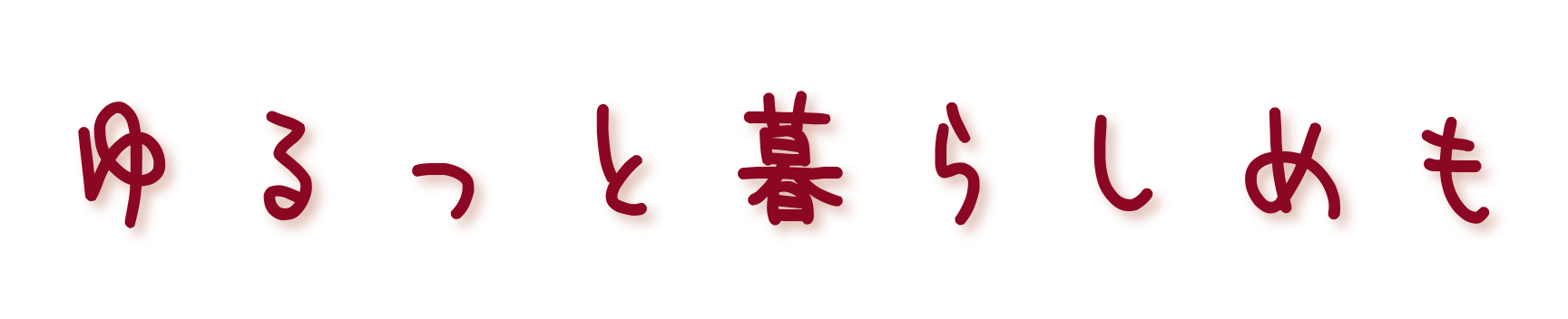年末になると、玄関先に飾られるしめ縄や門松、そしてお供えの鏡餅。
でも「いつ飾ればいいの?」「どの日に片付けるのが正解?」と迷う人も多いのではないでしょうか。
正月飾りはただの飾りではなく、新しい年の福をもたらす“年神様”をお迎えするための大切な準備です。
この記事では、しめ縄・門松・鏡餅の飾る時期や片付けのタイミング、避けたほうがいい日、地域による違いなどをわかりやすく解説。
正しいマナーを知ることで、新しい一年を気持ちよく迎えることができます。
年末の忙しい時期でも迷わないように、ぜひ参考にしてみてください。
目次
正月飾りを飾る意味とは?
正月飾りを飾ることには、「見た目を華やかにする」以上の深い意味があります。
それは、新しい年の幸福をもたらしてくれる年神様(としがみさま)をお迎えするための準備。
古くから日本では、正月飾りを通して神様が迷わず家に来られるように整えるのが習わしとされてきました。
年神様を迎えるための準備
年神様は、その年の豊作や家族の健康、幸福をもたらすといわれる神様です。
その神様をお迎えするために、家の入り口を清めるしめ縄や門松を飾り、神様の居場所として鏡餅をお供えします。
つまり、正月飾りとは「神様を家に迎え入れるための目印」であり、神聖な空間づくりそのものなのです。
しめ縄・門松・鏡餅の役割の違い
- しめ縄:邪気を寄せつけず、清らかな場所であることを示す。
- 門松:神様が降り立つ“依り代(よりしろ)”としての目印。
- 鏡餅:年神様への供え物であり、神様が宿るとされる象徴。
この3つを揃えることで、家全体を清め、神様を正しくお迎えする準備が整います。
正月飾りを整える時期の由来
昔から日本では、12月13日を「正月事始め」として、掃除や飾り付けを始める日とされてきました。
この日から年末にかけて家を清め、正月飾りを整えることで、神様を気持ちよく迎える準備をします。
大掃除と正月飾りはセットで行うのが本来のしきたり。
単なる習慣ではなく、神様への敬意と感謝を表す行為なのです。
正月飾りはいつから飾る?縁起の良い日と避けたい日
正月飾りを出す日は、実は“いつでもOK”というわけではありません。
古くから日本では、縁起の良い日や避けるべき日があり、
それを意識して飾ることで、より良い一年を迎えられるといわれています。
ここでは、しめ縄・門松・鏡餅を飾るベストな日と、避けたい日を紹介します。
最も縁起の良い「28日」「30日」の理由
一般的に12月28日が最も縁起の良い日とされています。
「八(末広がり)」という数字が繁栄を意味し、新しい年を気持ちよく迎える準備に最適です。
また、12月30日も「きりの良い日」とされ、年末の忙しさを避けつつ落ち着いて飾れるタイミングです。
この2日間のどちらかに飾ると、縁起良く新年を迎えられるといわれています。
避けるべき「29日」「31日」の意味
12月29日は「二重苦」や「苦の日」と読まれることから、昔から避ける風習があります。
また、12月31日は「一夜飾り」と呼ばれ、神様への準備が慌ただしい印象になるため不吉とされます。
特に31日に飾るのは「葬儀の一夜飾り」を連想させることから、神様に失礼と考えられています。
どうしても遅れる場合でも、できれば29日と31日は避けるのが望ましいでしょう。
地域別の飾り始め(関東と関西の違い)
関東では、12月28日までに飾り付けを終える家庭が多く、「松の内」が1月7日までとされるのが一般的です。
一方、関西では1月15日までを松の内とする地域が多く、そのため飾り始めや片付けの時期も少しゆるやかです。
いずれの場合も、「神様を丁寧にお迎えする」という心構えが大切です。
正月飾りはいつまで飾る?片付けのタイミングと注意点
お正月が過ぎると、「正月飾りっていつまで飾っておくの?」という疑問が出てきますよね。
実は、この片付けの時期にもきちんとした意味があります。
縁起を大切にするためにも、地域の習わしに合わせて正しいタイミングで片付けることが大切です。
「松の内」までが一般的|地域による違い
正月飾りは、年神様が家に滞在するとされる「松の内」まで飾るのが一般的です。
関東では1月7日まで、関西では1月15日までが目安。
松の内が明けると、神様が天に帰られるといわれており、その日を境に飾りを外すことで、感謝と区切りの意味を持たせます。
片付ける日は「1月7日」または「15日」
飾りを片付ける日は、松の内の最終日が基本です。
関東では1月7日(人日の節句)、関西では1月15日(小正月)に外すのが伝統。
ただし、仕事の都合などで難しい場合は、週末などに早めに外してもOKです。
大切なのは、感謝の気持ちを込めて片付けるという心構えです。
「どんど焼き」で感謝を伝えてお焚き上げ
外した正月飾りは、地域の神社やお寺で行われる「どんど焼き」でお焚き上げします。
火にくべることで、年神様を送り出し、その年の無病息災を祈願する行事です。
もし近くにどんど焼きがない場合は、新聞紙などに包んで感謝を込めて処分するのでも構いません。
燃えるゴミとして出す場合も、他のゴミとは分けて丁寧に扱いましょう。
正月飾りを飾るときの基本マナー
正月飾りを飾るときは、見た目だけでなく飾る位置や向き、扱い方にも決まりがあります。
これを知っておくことで、神様に対して失礼のないお迎えができ、より清らかな気持ちで新年を迎えることができます。
しめ縄の位置と向き
しめ縄は「ここは神聖な場所である」ということを示すための飾りです。
玄関や神棚、台所などの入口に飾るのが一般的で、人が出入りする上部の中央に掛けます。
向きは「正面から見て左右対称」になるよう整えるのが基本。
また、飾る前には軽く埃を払い、清潔な状態にしてから掛けるようにしましょう。
門松の設置場所と注意点
門松は、年神様が降り立つ目印(依り代)とされる飾りです。
一般的には、門の両側や玄関前の左右に1対で飾るのが正式な形。
竹の切り口が斜めになっているのは「笑い口」と呼ばれ、神様を喜んで迎える意味があります。
通行の邪魔にならない位置に設置し、倒れないようにしっかり固定しましょう。
鏡餅を飾る場所と縁起の意味
鏡餅は年神様へのお供え物であり、神様が宿る場所とされています。
飾る場所は、神棚や床の間、または家族が集まるリビングなど清らかな場所が最適。
また、鏡餅の丸い形には「円満」や「調和」の意味が込められています。
飾る際は直射日光を避け、清潔な台(お三方など)の上にのせるのが基本です。
さいごに
正月飾りを整えることは、単に縁起を担ぐ行為ではなく、新しい年を迎える自分や家族の心を整える時間でもあります。
しめ縄や門松、鏡餅を丁寧に飾ることで、自然と心が清められ、穏やかな気持ちで新年を迎えられるはずです。
年神様をお迎えする準備を通して、「一年を大切に始めたい」という想いを形にする——
それが日本のお正月文化の魅力です。
ぜひ今年は、飾る日や片付けの意味を意識しながら、家族みんなで正月飾りを楽しんでみてください。